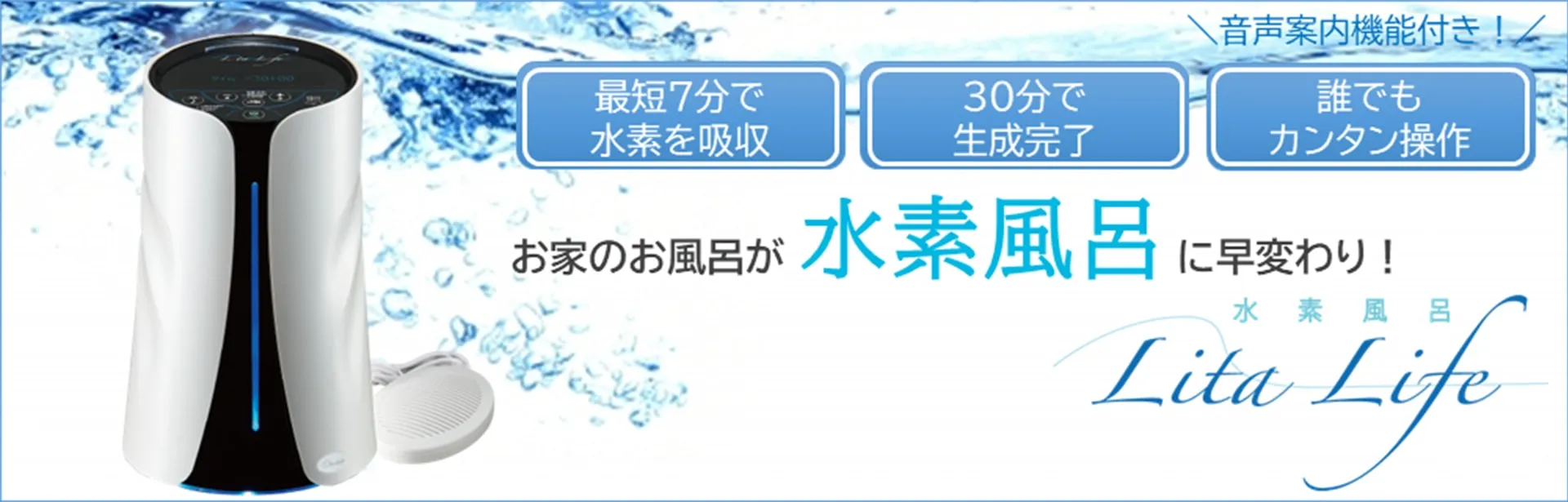【水選びの決定版】硬水と軟水、あなたに合うのはどっち?メリット・デメリットと使い分けガイド

「このミネラルウォーターは硬水だから、少し飲みにくいかも」「和食には日本の軟水が合う」。
私たちは何気なく「硬水」「軟水」という言葉を使っていますが、その違いを正確に説明できるでしょうか?
実は、この違いを理解するだけで、いつもの料理が格段においしくなったり、ご自身の体調やライフスタイルに合う水を選べるようになったりします。
この記事では、硬水と軟水を分ける「硬度」の正体から、それぞれのメリット・デメリット、そして料理や飲み物といった生活シーン別の使い分けまで、分かりやすく徹底解説します。
1. 硬水と軟水の違いは「硬度」!その正体と基準を解説
硬水と軟水を明確に区別する尺度が「硬度(こうど)」です。
まずは、この硬度の正体と分類について詳しく見ていきましょう。
目次
1-1. 「硬度」とは?カルシウムとマグネシウムの量で決まる
水の硬度とは、水1リットルあたりに含まれる「カルシウム」と「マグネシウム」のイオン量を数値化した指標です。
これらのミネラルが多く含まれていれば「硬度が高い(=硬水)」、少なければ「硬度が低い(=軟水)」となります。
日本では一般的に、以下の計算式(アメリカ硬度)が用いられます。
硬度(mg/L)=(カルシウム量mg/L×2.5)+(マグネシウム量mg/L×4.1)
商品ラベルに記載されている硬度の数値を確認するのが、もっとも確実な方法です。
1-2. WHOの基準で見る硬水・軟水の分類
硬度の基準はいくつかありますが、世界保健機関(WHO)の基準をもとにした一般的な分類は以下のとおりです。
●軟水:硬度0~60未満
●中程度の軟水:硬度60~120未満
●硬水:硬度120~180未満
●非常な硬水:硬度180以上
一般的に、硬度120mg/Lを境に、それ未満を「軟水」、以上を「硬水」と呼びます。
ちなみに、日本の水道水の平均硬度は50~60mg/L前後で、そのほとんどが「軟水」に分類されます。
例えば、フランスの「エビアン」(約304mg/L)は硬水、日本の「サントリー天然水(南アルプス)」(約30mg/L)は軟水に分類されます。
1-3. 日本が軟水、ヨーロッパが硬水に多い理由
この違いは、国の地形や地質に由来します。
- 日本(軟水):国土が急峻で、降水が地中にとどまる時間が短いため、水がミネラルをあまり含まない「軟水」になります。
- 日本の水道水もほとんどが軟水です。
- ヨーロッパ(硬水):なだらかな地形で、水が石灰岩の地層を時間をかけて通過します。
- その過程でミネラルが豊富に溶け出すため、「硬水」が多くなります。
このように、水の硬度はその土地の地質的な特徴が反映されたものなのです。
2. メリット・デメリット比較!硬水と軟水、あなたに合うのはどっち?

硬水と軟水には異なる特徴があります。
ご自身の体調や目的に合わせて選んでみましょう。
2-1. 【硬水】のメリットとデメリット
《メリット》
最大のメリットは、骨や歯の形成に必要なカルシウムや、体の調子を整えるマグネシウムといったミネラルを飲むだけで手軽に補給できる点です。
運動後の水分補給や、食生活が乱れがちな方のミネラル補給源として注目されます。
一部では、硬水地域の健康データに関する研究報告もあり、その関連性が注目されることもあります。
《デメリット》
ミネラルが多いため口当たりが重く、苦みを感じることがあります。
また、マグネシウムの性質上、胃腸が敏感な方や飲み慣れていない方が一度にたくさん飲むと、おなかがゆるくなることがあります。
乳幼児や腎臓疾患などでミネラル摂取の制限がある方は、飲用を避けるか、事前に医師に相談しましょう。
生活面では、加熱するとミネラルが結晶化し、電気ケトルなどに白い「スケール」として付着しやすいという側面もあります。
2-2. 【軟水】のメリットとデメリット
《メリット》
ミネラル含有量が少ないため、口当たりがまろやかでクセがなく、ごくごくと飲みやすいのが特徴です。
日常的な水分補給に適しているといえます。
また、クセがないため素材本来の繊細な風味を邪魔せず、和食やコーヒー、お茶などをいれるのにも合うでしょう。
肌や髪への刺激が少なく、ミネラルによるタンパク質への影響が少ないため、髪のきしみが少なく肌のつっぱり感も感じにくいといわれています。
石けんや洗剤の泡立ちがよいのも利点です。
《デメリット》
飲みやすい反面、ミネラル含有量は少なくなります。
そのため、水分補給と同時にミネラルも積極的に摂取したいという目的にはあまり向いていません。
3. 生活シーン別!硬水と軟水の使い分けガイド
硬水と軟水の特徴を理解すれば、日々の生活に合う水を選ぶことができます。
3-1. 【料理編】和食・洋食との相性
- 和食(だし、炊飯)には「軟水」
昆布やかつお節のうま味成分は、軟水でよく引き出されます。 - また、お米を炊く際も軟水のほうが合います。
- 硬水で炊くと、カルシウムがお米の食物繊維を硬化させ、パサついた食感になることがあるでしょう。
- 野菜を柔らかく煮込みたい場合も軟水が向いています。
- 洋食(肉の煮込み、パスタ)には「硬水」
ビーフシチューなど肉を煮込む料理では、硬水が肉の臭み成分をアクとして排出しやすくしてくれます。 - パスタをゆでる際も、硬水を使うとデンプンとミネラルが結合し、コシのある仕上がりになります。
- ジャガイモなど、煮崩れさせたくない食材の調理にも適しているといわれます。
3-2. 【飲み物編】コーヒー・お茶・ウイスキー
- コーヒー:豆の酸味や香りを楽しみたいなら「軟水」、苦みやコクを際立たせたいなら「硬水」が向いています。
- お茶:緑茶の繊細な風味を引き出すには「軟水」が合います。
- 紅茶の場合は、軟水だと香り高く、硬水だと色が濃く出る傾向があります。
- ウイスキー:重厚な味わいの銘柄には、仕込み水として硬水が使われることがあります。
- ミネラルが酵母の働きに影響を与え、複雑な味わいを生み出すからです。
3-3. 【乳幼児編】赤ちゃんのミルク作りは「軟水」が基本
赤ちゃんのミルクを作る際は、必ず「軟水」を使いましょう。
粉ミルクは、それだけで赤ちゃんに必要なミネラルが完璧なバランスで配合されています。
ミネラル豊富な硬水を使うと、過剰摂取となり、赤ちゃんの未熟な腎臓や消化器官に負担をかける可能性があるのです。
海外旅行の際は現地の水道水が硬水のことも多いため、市販のベビー用ウォーターを使用すると安心です。
まとめ

今回は、硬水と軟水の違いについて、その基準から私たちの生活への影響、具体的な使い分けまでを解説しました。
水の「硬度」という個性を理解することで、日々の料理や飲み物がより一層味わい深くなり、ご自身の体調に合わせた水選びも可能になります。
ぜひ、今日からミネラルウォーターのラベルを確認して、ご自身のライフスタイルに最適な水を見つけてみてください。
さて、これまで見てきたように、水には「硬度」という重要な個性があります。
しかし、水選びをさらに意識するなら、水の個性はそれだけではありません。
硬度という視点とは別に、水に「プラスアルファの価値」を持たせるという新しい水選びがあります。
その一つが、日々の水に「水素」をプラスするという選択です。
リタハートインターナショナル株式会社の「リタアクア」は、いつもの水から手軽に水素水を作ることができる製品です。
体をいたわる中性に近い水質にこだわりながら、日々の水分補給をサポートします。
水の硬度を選ぶように、これからは水に含まれる「成分」も選ぶ時代へ。
リタアクアで、ワンランク上の水分補給を始めてみませんか?